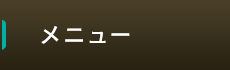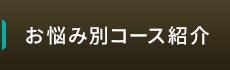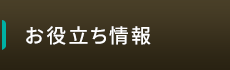急性期の圧迫について
急性期の肉離れに対する適切な圧迫(Compression)は、国際的な応急処置のガイドライン(RICE/PRICE/POLICE原則)において推奨されている基本的な処置です。
不適切な圧迫や過度な圧迫が循環障害を引き起こすリスクはありますが、正しい圧迫の目的は「内出血と腫れを最小限に抑え、治癒を促進すること」です。
肉離れの応急処置における「圧迫」の真実:腫れと内出血を最小限に抑え、早期回復を目指すための適切な知識
太ももの肉離れ(筋挫傷や筋断裂)は、スポーツ現場で最も頻繁に発生する怪我の一つです。激しい痛みと共に機能が失われ、その後の競技復帰までに数週間から数ヶ月を要することもあります。
受傷直後の応急処置は、その後の回復速度を大きく左右します。この応急処置の基本原則として広く知られているのが「RICE(ライス)」原則です。現在では、より安全かつ積極的なアプローチを組み込んだ「PRICE」や「POLICE」などの原則が提唱されていますが、その中心には必ず「圧迫(Compression)」が含まれています。
しかし、「圧迫をすると血行が悪くなり、かえって治りが悪くなるのではないか」という懸念を持つ方がいます。これは、圧迫を「単に強く締め付けること」と誤解しているために生じる懸念です。実際には、適切な圧迫は治癒を助けますが、誤った圧迫は深刻な問題を引き起こす可能性があります。
1.なぜ急性期の肉離れに「圧迫」が必要なのか
肉離れが発生すると、筋肉組織や血管が損傷し、出血とそれに伴う炎症が起こります。この炎症反応の結果として、患部は腫れ上がり(浮腫)、痛みが強くなります。
(1) 組織の腫れ(浮腫)を最小限に抑える
炎症によって生じた余分な水分(浮腫)は、細胞間のスペースを広げ、酸素や栄養素が損傷組織に到達するのを妨げます。また、腫れ自体が周囲の正常な血管や神経を圧迫し、さらなる二次的な損傷(二次性低酸素障害)を引き起こす可能性があります。
適切な圧迫は、外部から患部に均等な圧力をかけることで、血管の外への血液や組織液の漏出を物理的に抑え、腫れの拡大を効果的に最小限に食い止めます。腫れが少なければ少ないほど、組織への酸素供給が保たれ、回復プロセスがスムーズに開始されます。
(2) 内出血をコントロールする
肉離れの直後、損傷した血管からの出血は収まるまでに時間がかかります。圧迫は、この内出血を早期に止め、血腫(血の塊)の形成を抑えるのに役立ちます。大きな血腫は、その後、硬い線維組織(瘢痕組織)に置き換わりやすく、これが筋肉の柔軟性や強度を低下させ、再発のリスクを高める最大の要因となります。
つまり、圧迫の目的は「血流を止める」ことではなく、「内出血と炎症反応の過剰な拡大を防ぐ」ことなのです。
2.「不適切な圧迫」が治癒を妨げるメカニズム
「圧迫が治りを悪くする」という懸念は、主に過度な圧迫や誤った圧迫方法によって現実化するリスクを指しています。不適切な圧迫は、本来の目的とは逆に、以下のような悪影響を及ぼします。
(1) 循環障害による組織の壊死(虚血)
最も深刻なリスクが、過度な圧迫による動脈血流の阻害です。弾性包帯やサポーターをあまりにも強く巻きすぎると、損傷部位よりも末梢(肉離れが太ももなら膝から下、足先など)への血液供給が遮断されてしまいます。
血液が途絶えると、酸素や栄養素が届かなくなり、筋肉や神経などの組織は虚血状態に陥ります。この状態が長く続くと、組織が不可逆的に壊死(えし)し、重度の後遺症を残したり、最悪の場合はコンパートメント症候群(区画症候群)と呼ばれる緊急事態に発展したりする可能性があります。
循環障害のサインとしては、圧迫部より末梢の皮膚の色が紫色や青白く変化する、感覚が麻痺する、強いしびれや冷感が生じる、などが挙げられます。これらのサインが見られた場合は、直ちに圧迫を緩める必要があります。
(2) 組織の固定化と柔軟性の低下
単に強く圧迫するだけでなく、不均一な圧迫は、筋肉の正しい配列での修復を妨げることがあります。また、損傷部位をギプスのように完全に固定しすぎると、過度な安静と同様に、線維化(瘢痕組織の形成)を促進し、筋肉の柔軟な修復を妨げてしまいます。
現在推奨されているPOLICE原則(Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation)の「Optimal Loading(適切な負荷)」は、過度な安静を避け、痛みのない範囲で早期に適切な運動負荷をかけることで、修復組織の柔軟性を高め、強い筋肉への再生を促すという考え方に基づいています。不適切な圧迫による固定化は、この最適な負荷のプロセスを妨げます。
3.早期回復のための「適切な圧迫」の実施方法
適切な圧迫は、循環障害を引き起こさず、内出血と腫れだけを抑え込む「均等で心地よい圧力」をかけることです。
(1) 圧迫材の選び方と巻き方
- 圧迫材の選択: 弾性包帯(バンデージ)が最も推奨されます。テーピングも可能ですが、巻き始めと巻き終わりに差が出やすく、調整が難しいため、弾性包帯の方が均等な圧迫をかけやすいです。
- 巻き方の基本: 圧迫は、怪我の部位よりも末梢側(体から遠い方)から巻き始め、中枢側(体に近い方)に向かって巻き上げます。この巻き方は、静脈血やリンパ液を心臓へ戻す流れを助け、腫れが末梢に溜まるのを防ぐ「圧勾配」を作り出すために非常に重要です。
- 圧力の調整: 「きつすぎず、緩すぎない」圧力をかけます。指が何とか入る程度で、巻いた後も足指の色や感覚に異常がないことを確認してください。
(2) 圧迫を実施する時間帯
圧迫は、内出血と腫れが最も進行しやすい受傷直後から48時間〜72時間(炎症の急性期)が特に重要です。この間、冷却(Ice)と挙上(Elevation)と組み合わせることで、最大の効果を発揮します。睡眠時も可能であれば圧迫を維持することが望ましいですが、その際も循環障害が起こらないよう、締め付けすぎないよう注意が必要です。
急性期の圧迫についてのまとめ
肉離れに対する圧迫は、回復を早めるための応急処置です。過度で不適切な圧迫は循環問題などを起こします。適切な圧迫が重要です。
急性期の正しい対応は、「RICE/POLICE原則に基づき、末梢から中枢に向けて、指の色や感覚に異常が出ない程度の均等な圧力で圧迫する」ことです。受傷した場合は、まずこれらの応急処置を行い、その後は速やかに医療機関を受診し、正確な診断と最適な負荷(Optimal Loading)によるリハビリテーションを開始することが、安全かつ早期に競技復帰するための鍵となります。
急性期をすぎてからの圧迫について
急性期を過ぎて競技に復帰した際、テーピングやサポーターによる過度な圧迫は、主にパフォーマンスの低下や皮膚・末梢神経への悪影響を及ぼします。
競技復帰時のテーピングやサポーターの目的は、筋肉の過度な伸張を制限し、再発を予防すること、および患部の不安感を軽減することです。しかし、この予防的な圧迫が強すぎたり、長時間に及んだりすると、以下のような悪影響が生じる可能性があります。
競技復帰時のサポーター・テーピングによる圧迫がもたらす影響
急性期を過ぎて競技に復帰する際、サポーターやテーピングによる過度な圧迫は、肉離れの治癒を直接的に妨げる重篤な循環障害を引き起こすリスクは低いものの、パフォーマンスの低下や皮膚・末梢神経への悪影響を及ぼす可能性があります。
競技復帰時の圧迫の目的は、筋肉の過度な伸張を制限し、再発を予防することと、患部の不安感を軽減することです。
1.テーピングによる圧迫の影響
テーピングは、筋線維の走行に合わせて巻き、筋肉の動きをピンポイントで制限し、サポートすることに長けています。
- 血流の物理的な制限: テーピングが皮膚や筋膜に対して強い圧力をかけると、局所の毛細血管や静脈の血流が圧迫され、滞る可能性があります。これにより、運動中に生じる代謝老廃物(乳酸など)の除去が遅れ、疲労の蓄積やパフォーマンスの低下を招くことがあります。
- 筋力と可動域の制限: テーピングの圧迫が強すぎたり、関節の動きを不必要に制限したりすると、筋肉本来の最大収縮力の発揮が妨げられ、パフォーマンスが低下します。
- 皮膚・末梢神経の圧迫: 強い張力による持続的な圧迫や摩擦が、皮膚の炎症や水ぶくれを引き起こすほか、浅い位置にある末梢神経を圧迫し、しびれや感覚異常(ピリピリ感、鈍麻)を生じさせることがあります。
2.サポーターによる圧迫の影響
サポーター(スリーブタイプ、ベルトタイプなど)は、テーピングに比べて広範囲に均一な圧迫を提供し、着脱が容易であるという特性があります。
- 循環への影響(広範囲の均一圧): サポーターは、一般的にテーピングのような局所的な強い張力をかけにくい反面、広範囲の静脈血やリンパ液の還流を阻害する可能性があります。特に、太ももの付け根や膝裏など、関節をまたぐ部分でサポーターが折れ曲がったり、縁が食い込んだりすると、その部分で強い圧力がかかり、むくみ(浮腫)が生じやすくなり、疲労回復の遅延につながります。
- 筋ポンプ作用の阻害: サポーターが強すぎる場合、筋肉の収縮・弛緩による筋ポンプ作用(静脈血を心臓へ戻す働き)が妨げられ、テーピングと同様に疲労物質の除去が遅れやすくなります。
- 熱と皮膚トラブル: サポーターは通気性が悪い素材の場合、運動中の熱がこもりやすく、汗による皮膚の浸軟(ふやけ)や、かゆみ、皮膚炎の原因となりやすいです。
- サポート力の限界と依存: サポーターは均一に圧迫するため、筋肉の特定の動きを止める能力はテーピングに劣ります。にもかかわらず、強い安心感から過度に依存してしまうと、根本的な筋力・柔軟性の改善を怠り、サポーターなしでは再発リスクが高まるという悪循環に陥る可能性があります。
3.正しい圧迫利用のための原則
競技復帰時のテーピングやサポーターは、「圧迫よりも機能的なサポート」を第一に考えるべきです。
- サポート力と循環のバランス: 筋肉の過伸展を防ぐ程度の適切な張力に留めます。着用後、足先や指の色、しびれがないかを確認し、少しでも違和感があればすぐに緩めるか、取り外します。サポーターを選ぶ際は、サイズが適切で、縁が皮膚に食い込まないものを選びましょう。
- 筋力回復の妨げにならないこと: 圧迫具はあくまで補助的なツールであり、患部の筋力や柔軟性が回復するまでの一時的な手段と位置づけるべきです。装着することで、本来行うべきリハビリや筋力トレーニングが疎かになってはなりません。
- 長時間の装着を避ける: 運動中や必要な時以外はサポーターやテーピングを外し、筋肉を解放して血行を促進することが、疲労回復と皮膚の健康維持に繋がります。
最終的な再発予防は、テーピングやサポーターに頼るのではなく、患部の柔軟性、筋力、そして動作の改善によって達成されることを理解し、専門家の指導のもとで段階的に負荷を上げていくことが最も重要です。
当院ではサポーターやテーピングなしでの復帰を目指して治療をしております。
肉離れになってしまった直後でも、肉離れの痛みがなかなか取れずに長引いている方でも、1度ご相談いただければと思います。
院情報
Sprout整骨院
住所:埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目19-4 P’sスクエア常盤2F
JR京浜東北線「北浦和駅」西口から徒歩2分
TEL:048-762-7966
公式LINE:LINEでのお問い合わせはこちら
埼玉県さいたま市の整骨院・整体なら『Sprout整骨院』へ。
当院ではスポーツ外傷・障害に特化した施術を行なっています。
捻挫・肉離れで治癒まで期間がかかるスポーツ外傷を早期復帰させる外傷に特化した施術を行なっています。 またどこに行っても改善されなかった痛みでお困りでしたら、Sprout整骨院へお越し下さい。
夜21時まで営業していますので、部活帰り、お仕事帰りの方にもとても通いやすくなっています。
どこに行っても改善されないスポーツ時の痛み、慢性痛、身体の不調でお困りでしたら、ぜひご相談ください!