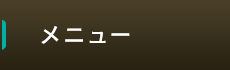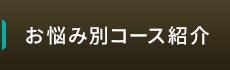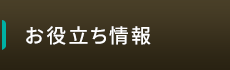三角骨障害と足首の深い関連性:痛みの原因と予防策
三角骨障害は、足首、特に後方の痛みの原因として知られていますが、その痛みは単に「骨があるから」という単純なものではありません。足首の特定の動きと深く関連しており、アスリートやダンサーに多く見られる特徴的な病態です。ここでは、三角骨障害のメカニズムと、なぜ足首の動きが重要になるのかを、専門的な視点から詳しく解説します。
1. 三角骨とは何か?
三角骨とは、足首の関節を構成する脛骨と距骨の後方に位置する、小さな余分な骨のことです。これは、生まれつき存在する場合もあれば、成長過程で骨が完全に癒合しなかったために生じることもあります。一般的に、人口の約10〜25%に存在すると言われており、必ずしもすべての人に症状が出るわけではありません。つまり、三角骨があること自体が問題なのではなく、その骨が周囲の組織と衝突(インピンジメント)を起こすことが、痛みの根本原因なのです。
2. 足首の「底屈」が引き起こす衝突
三角骨障害の最も大きな特徴は、足首を極端に「底屈」させた時に痛みが生じることです。底屈とは、つま先を床に向かって伸ばす、バレエのポワントやサッカーボールを蹴る際の動作です。
この底屈動作時に、脛骨の後端と、かかとの骨である踵骨(しょうこつ)が、その間に存在する三角骨を挟み込むような形になります。この挟み込みによって、三角骨そのもの、あるいは三角骨の周囲にある後方距骨関節包(足首を包む膜)や長母趾屈筋腱(ちょうぼしくっきんけん)といった軟部組織が強く圧迫・刺激されます。この機械的なストレスが、炎症や痛み、腫れを引き起こすのです。
そのため、バレエダンサー、サッカー選手、マラソンランナー、あるいはつま先立ちを多用する職種の人々など、足首を繰り返し底屈させる動作を行う人に、この障害が多く見られます。
3. 「背屈」制限が痛みを悪化させるメカニズム
三角骨障害は、底屈の動きで起こるものですが、その根本には「背屈(はいくつ)」の制限が関わっているケースが少なくありません。背屈とは、足の甲をすねに近づける、しゃがんだり歩いたりする際に重要な動きです。
足首の背屈の可動域が狭いと、歩行や走行時に、本来背屈で吸収すべき衝撃や動きを、別の関節で代償しようとします。そして、体を前に進める推進力を得るために、下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)が過剰に働き、足首の底屈を強めることになります。
つまり、「足首が硬い(背屈ができない)→底屈に頼った動作になる→三角骨周辺へのストレスが増える」という悪循環が生まれます。このように、足首の柔軟性の欠如が、三角骨障害の痛みを引き起こす一因となるのです。
三角骨障害は、単に「骨のせい」ではなく、足首の機能不全が引き起こす痛みです。自身の足首の状態を理解し、適切なケアと予防を行うことで、痛みなくスポーツや日常生活を送ることが可能になります。
当院では三角骨障害に対して、手術などではなく徒手療法での施術を行っております。
大会・舞台の前で手術する時間はないけど、痛みはなんとかしてほしい、という方は多いのではないでしょうか?
そんな方は、当院に1度ご相談いただければと思います!
院情報
Sprout整骨院
住所:埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目19-4 P’sスクエア常盤2F
JR京浜東北線「北浦和駅」西口から徒歩2分
TEL:048-762-7966
公式LINE:LINEでのお問い合わせはこちら
埼玉県さいたま市の整骨院・整体なら『Sprout整骨院』へ。
当院ではスポーツ外傷・障害に特化した施術を行なっています。
捻挫・肉離れで治癒まで期間がかかるスポーツ外傷を早期復帰させる外傷に特化した施術を行なっています。 またどこに行っても改善されなかった痛みでお困りでしたら、Sprout整骨院へお越し下さい。
夜21時まで営業していますので、部活帰り、お仕事帰りの方にもとても通いやすくなっています。
どこに行っても改善されないスポーツ時の痛み、慢性痛、身体の不調でお困りでしたら、ぜひご相談ください!